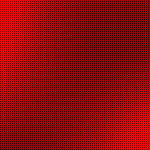こんにちは。イノベーション推進コンサルタントの鈴木です。今回は、グループ企業がイノベーションを効果的に推進するための具体的な方法について、お話ししたいと思います。
近年、あらゆる業界で技術革新やビジネスモデルの変化が加速しており、イノベーションは企業の生き残りに不可欠な要素となっています。特にグループ企業の場合、複数の事業領域を持つがゆえに、イノベーションの機会も多岐にわたります。
しかし、グループ企業ならではの課題もあります。各社の文化や体制の違いが、イノベーションの阻害要因になることも少なくないのです。
そこで本記事では、私がこれまでグループ企業の支援で蓄積してきたノウハウをもとに、イノベーション推進のための3つのポイントを詳しく解説します。
- イノベーションを推進する組織文化の醸成
- イノベーションを生み出す人材の育成と獲得
- イノベーションプロセスの確立と運用
これらを着実に実行することで、グループ企業は全社的なイノベーションを加速させることができるはずです。それでは、早速見ていきましょう。
目次
イノベーションを推進する組織文化の醸成
イノベーションを推進するには、それを支える組織文化が不可欠です。以下の3点を意識して、文化醸成に取り組んでいきましょう。
失敗を許容する環境づくり
イノベーションは、試行錯誤の連続です。失敗を恐れず、新しいことにチャレンジできる環境を整えることが重要です。
そのためには、トップ自らが「失敗を許容する」姿勢を明確に示すことが効果的です。例えば、私が支援したA社では、社長が「失敗したプロジェクトの事例共有会」を定期的に開催し、失敗から学ぶ文化を根付かせました。
また、失敗を評価につなげない工夫も必要です。チャレンジした結果ではなく、そのプロセスを評価する仕組みを取り入れるのも一案です。
多様性を尊重するマインドセットの醸成
イノベーションは、多様な視点やアイデアの交流から生まれます。年齢、性別、国籍、専門分野などの多様性を尊重し、活かすマインドセットを醸成しましょう。
B社では、「ダイバーシティ&インクルージョン宣言」を行い、多様性を尊重する企業文化づくりに舵を切りました。社内報やイントラネットで、多様なバックグラウンドを持つ社員を定期的に紹介する取り組みなどが功を奏し、イノベーティブなアイデアが次々と生まれています。
自律性を重視したマネジメントスタイルの導入
イノベーションには、社員の自律性が欠かせません。一人ひとりが主体的に考え、行動できる環境を整える必要があります。
C社では、「ジョブ型雇用」を導入し、社員の自律性を後押ししました。業務内容と求める成果を明確にすることで、社員は自らの裁量で仕事を進められるようになったのです。
また、マネージャーには、部下の自律性を引き出すコーチング型のマネジメントスタイルを浸透させました。その結果、社員のモチベーションとイノベーションマインドは大きく向上しました。
イノベーションを生み出す人材の育成と獲得
イノベーションは、それを生み出す人材なくして実現しません。人材の育成と獲得は、イノベーション推進の要です。
イノベーション人材のスキルセットの定義
まず、自社に必要なイノベーション人材のスキルセットを明確にしましょう。専門性はもちろん、好奇心、創造性、チャレンジ精神などの資質も重要です。
D社では、「イノベーション人材要件」を策定し、社内外に公表しました。この要件に基づいて採用や育成を行うことで、イノベーション人材のパイプラインを太くしていったのです。
社内育成プログラムの設計と実行
イノベーション人材を社内で育成するには、戦略的なプログラム設計が不可欠です。offーJTだけでなく、OJTやジョブローテーションなども効果的に組み合わせましょう。
E社では、「イノベーションカレッジ」という育成プログラムを立ち上げました。社外の専門家を招いた講義や、他社との合同ワークショップなどを通じて、イノベーションスキルを体系的に身につけられる仕組みです。修了者からは、次々とイノベーティブなプロジェクトが生まれています。
外部からのイノベーション人材の獲得
社内育成と並行して、外部からイノベーション人材を獲得することも重要です。多様な知見や経験を持つ人材が加わることで、組織の発想力は大きく広がります。
F社では、「イノベーションスカウト制度」を設けました。社員が社外のイノベーション人材を推薦し、採用につなげる仕組みです。推薦者にはインセンティブを提供することで、全社的な「イノベーション人材探し」が活発化しました。
イノベーションプロセスの確立と運用
イノベーションを持続的に生み出すには、そのプロセスを確立し、着実に運用することが重要です。
アイデア創出プロセスの設計
まず、アイデアを生み出すプロセスを設計しましょう。社内外の知見を取り入れながら、多様なアイデアが生まれる仕掛けを作ります。
G社では、「イノベーションラボ」を設置し、社員が自由にアイデアを提案できる場を設けました。提案されたアイデアは、社内外のエキスパートによる評価を受け、有望なものには予算と人員が投入されます。
プロトタイピングと検証の仕組み構築
アイデアを具現化し、その価値を検証するプロセスも必要です。プロトタイピングと検証の仕組みを構築し、迅速かつ効率的に進められるようにします。
H社では、「ラピッドプロトタイピング」の手法を全社で共通言語化しました。アイデアをできるだけ早く形にし、ユーザーの反応を素早く取り入れる文化が根付いています。これにより、開発サイクルが大幅に短縮され、イノベーションスピードが加速しました。
事業化に向けた意思決定プロセスの確立
イノベーションを事業化するには、適切な意思決定プロセスが欠かせません。技術的実現性だけでなく、事業性や収益性の観点からも評価する必要があります。
I社では、「イノベーション評価会議」を設置し、事業化に向けた意思決定を行っています。会議メンバーには、技術部門だけでなく、事業部門や財務部門のメンバーも加わり、多角的な視点で評価が行われます。
まとめ
イノベーションは、グループ企業の持続的成長に欠かせない要素です。本記事では、イノベーション推進のための3つのポイントを詳しく解説しました。
- イノベーションを推進する組織文化の醸成
- イノベーションを生み出す人材の育成と獲得
- イノベーションプロセスの確立と運用
組織文化、人材、プロセスの3つの側面から、戦略的に取り組むことが重要だということがおわかりいただけたかと思います。
グループ企業では、各社の特性を活かしながら、全体最適でイノベーションを推進することが求められます。本記事の事例を参考に、自社に合ったイノベーション施策を立案し、実行していきましょう。
イノベーションは一朝一夕では実現しません。トップのコミットメントを得ながら、地道な努力を積み重ねることが成功の鍵を握ります。
グループの総力を結集し、イノベーションに挑戦し続ける。それが、激動の時代を勝ち抜く唯一の方法だと、私は確信しています。
皆様の取り組みを、心よりお祈り申し上げます。
【関連】ユニマット高橋洋二さんとは?
ユニマットグループの代表である高橋洋二氏は、1943年生まれの現在80歳の実業家だ。25歳で婦人服の輸入業として独立し、29歳で「ユニマットレディス」を立ち上げ全国に約300店舗を展開した。
その後、事業を飲食業や不動産業など多角化し、「ゆとりとやすらぎを提供する総合サービス集団」であるユニマットグループを築き上げた。2022年3月期のグループ連結売上高は1,628億円に上る。
高橋氏は「虹を見たければ、雨を楽しもう。」という言葉に象徴されるように、前向きな経営哲学を持つ。趣味はゴルフとクラシック音楽鑑賞で、現在は千葉県八街市で「八街未来都市」という大規模開発を進めている。
最終更新日 2025年6月9日