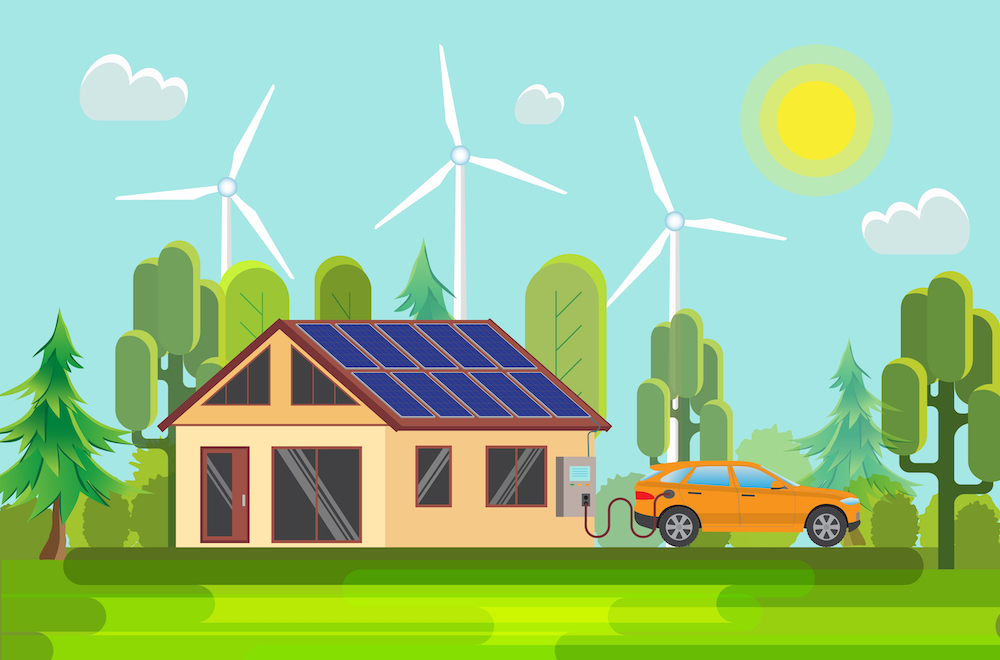「副収入が欲しい」
「株式会社ゴールドリンクの口コミが知りたい」
「株式会社ゴールドリンクの純金積立は資産運用としてどう?」
世の中が不景気になると同時に、お金の使い方に注目が集まっています。
お金を使うといっても、人によって使い方は異なりますが若い人に共通なのは、働いてもなかなかお金が増えないと言う現実ではないでしょうか。
お金を増やすためには様々な方法がありますが、1番安全な方法はサラリーマンあるいは公務員として働くことです。
しかしながら、そのような働き方では少し限界があると考えた方が良いかもしれません。
具体的にどのような限界があるかと言えば、昔のように昇給する事はあまり考えられないことです。
昔は、とにかくたくさんのお金をもらうことができましたが、最近はそのような傾向はなく、非常に苦しい状態が続いています。
若い人の収入が上がらなければ、結婚できない人も増えてしまい、現実的に考えて将来的に国自体が縮小傾向になるのは間違いないところです。
https://www.supercollidermusic.com/publisher-business.html
https://www.supercollidermusic.com/financial-planner-office.html
お金を手に入れるための副業などを始める
では、実際に現代の世の中を生きるにあたり、どのようなことをしておいたら良いのでしょうか。
それは単純に、サラリーマンあるいは公務員として働いていても良いですが、それだけではなく他の方法も考えることが必要です。
他の方法とは、つまりお金を手に入れるための副業などを始めるしかありません。
具体的には、空いた時間でアルバイトをしても良いですが、それでは増えるにしても限界があります。
そして、少なくともそれだと労働収入になってしまい、あまり有効のやり方とは言えません。
もし今よりも、あと月収50,000円だけ増やしたい場合には、それで良いかもしれませんが、そうすると結局睡眠時間まで削られてしまい、何も良い事はないでしょう。
このように考えるならば、まず資産運用を中心に考えた方が良いです。
資産運用自体は、特に時間はかかりません。
証券会社等の口座を開き後は投資信託などを行うことで実行されます。
投資信託を行った時、それぐらいのお金を出たら分割になるところですが、基本的にいくら入れても構いません。
最初からたくさん入れる必要はないといえます。
投資信託は継続をすることによって1つの結果を出す
最初からたくさんのお金を入れても良いですが、それがどのようになるかは分かりかねるところかもしれません。
基本的に、投資信託は継続をすることによって1つの結果を出すことができます。
継続すると言う事は、1ヵ月や2ヶ月でなく数年単位で行っていることに意味があるわけです。
もし、1年位で辞めてしまうのならば、そもそも投資信託自体はやめた方が良いかもしれません。
しかし、継続的に行うことができるならば、ぜひ積極的に投資信託に参加した方が良いです。
毎月出る金額は、無理のない金額を設定することが大事になります。
例えば、毎月50,000円以上入れることができる場合には、50,000円に設定しておくのが良いです。
もし100,000円入れることができる場合には、100,000円入れても良いですが、あくまで長期的な視点で考える必要があるため、たまたまその時用意できたお金が100,000円であり普段は30,000円しか用意できないとすれば、どちらかと言えば30,000円に設定した方が良いでしょう。
そして具体的に、計算してみることが重要になります。
計算した場合、本当にそれだけのお金が必要なのか考えてみることです。
金銭的にある程度余裕のある状態を維持しておいた方が良い
つまり、生活をする上で生活資金を減少させてまで行う必要はありません。
それよりも、金銭的にある程度余裕のある状態を維持しておいた方が良いといえます。
そのためには、毎月これだけ入れても問題ないと言う金額を入れそれができれば問題はないです。
投資信託で問題の安いのは、資金が減少したパターンになります。
投資信託をしていると、必ずと言っていいほど資金が減少するケースがあるわけです。
例えば毎月100,000ずつ入れた場合、10年後には12,000,000円のお金になっていますが、必ずしも通帳に12,000,000円のお金があるとは限らないといえます。
これはどのような状態かと言えば、投資をした株が下がり、結果的に減少してしまっている可能性があるわけです。
このような状態はよくあることですが、たいていはこの場合解約してしまう可能性が高くなります。
なぜ解約するかと言えば、心理的に結構厳しい状態に陥っているからでしょう。
お金を積み立てていたはずが、なぜか減少してしまっている状態を知ることになれば、もう継続しても落ちるだけだと考えます。
しかし実際には、株式は1つの特定の会社でなければ上がり下がりを送り返しますので、たまたまそれがそこだった時かもしれません。
まとめ
このときに売却してしまうと、自分の資金すら減らしてしまうことになります。
このような場合は、じっくりと耐えて元に戻るのを待ちましょう。
これにより、もしかしたら資金が何倍にも増える可能性はあります。
ただ現実的に考えると、1.1倍ぐらいに触れる程度になりますのであまり過剰な期待はしない方が良いです。
常にこれらのことを考えて、将来の資金を増やすべきです。
最終更新日 2025年6月9日